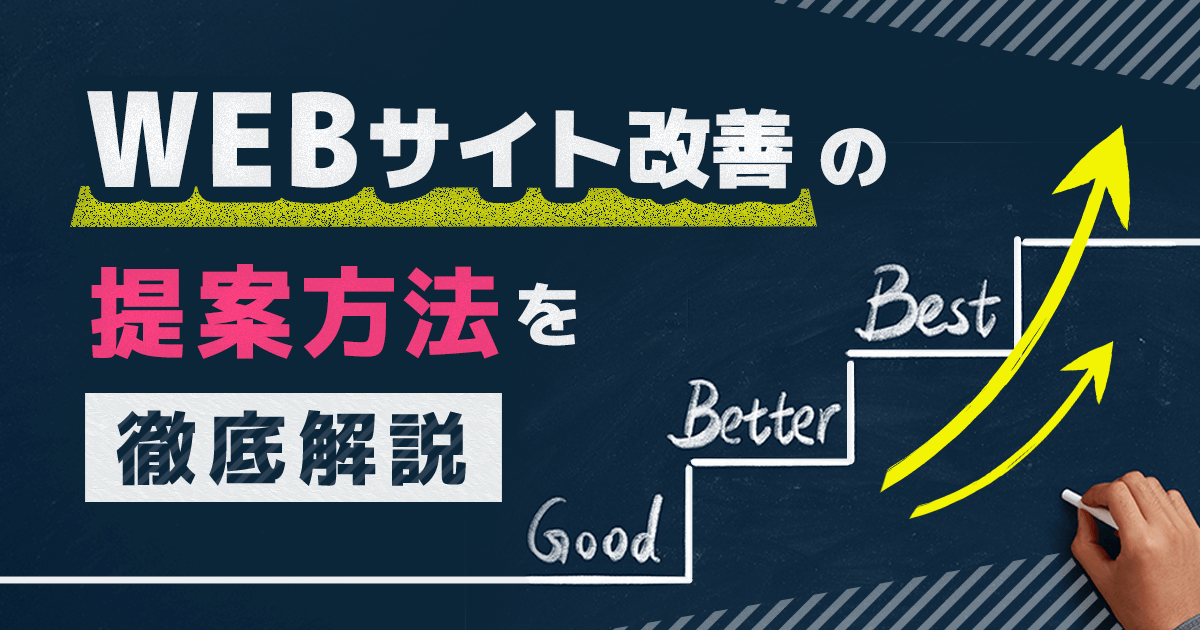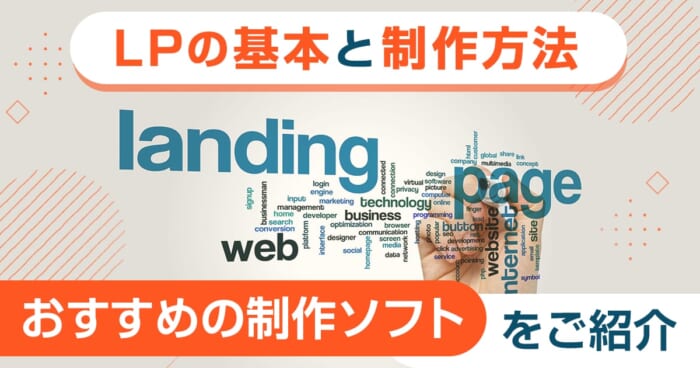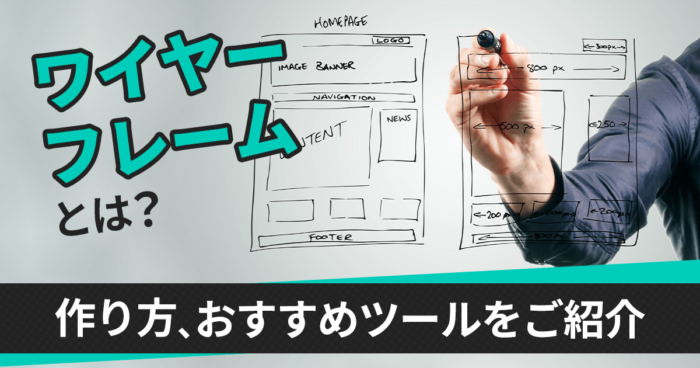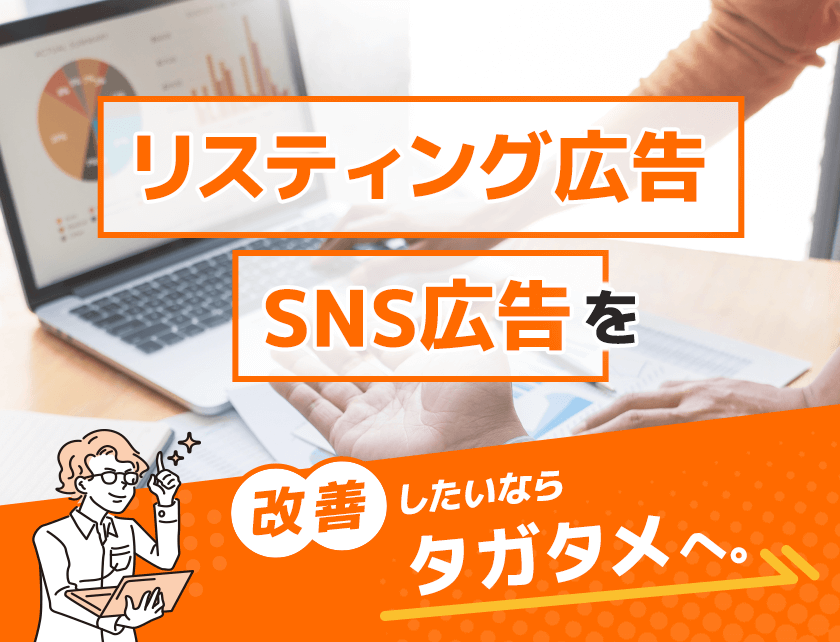WEBマーケティングでは、継続的なWEBサイトの改善が欠かせません。そのため、施策を実施する際は、サイト改善の提案を求められるケースも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、WEBサイト改善の流れから改善提案のポイントまで詳しく解説していきます。WEBサイト改善提案方法への理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
WEBサイト改善とは

WEBサイト改善とは、WEBサイトをより良くするための取り組みのことです。WEBサイト改善の目的は企業によっても異なりますが、主に「お問い合わせ(CV)を増やす」「認知を拡大させる」「利益を上げる」などが挙げられます。どのケースにおいても、企業の成長や拡大を目指して取り組むものだといえるでしょう。改善の効果を最大化するには、目標・目的やニーズに基づいた施策の検討が重要です。
改善のために検討すべき施策には大きく分けて、検索エンジンからの流入数を増やす「集客」にあたる外部の改善施策と、ユーザーアクションを促してCVRを増やしたり、ユーザビリティを改善したりする「接客」にあたる内部の改善施策があります。
外部の改善施策は、WEBサイトがどのような場所に露出しているか、流入経路は最適になっているか、効果の出やすい流入経路やアクセスを増やせる可能性のある経路はあるのか、といった検討からおこないます。ユーザーのデータを取得する場合、「Google Search Console(グーグルサーチコンソール)」や広告の管理機能、各SNSの解析機能などを利用するのが一般的です。
また、内部の改善施策は、WEBサイト内の導線やメニュー構成、フォームのレイアウト、コンテンツ内容などの検討から始めます。この場合に利用するのは、「Google Analytics(グーグルアナリティクス)」やヒートマップツールなどです。
WEBサイト改善の基本的な流れ

それでは、WEBサイトを改善する際はどのようにおこなうとよいいでしょうか。基本的な流れとしては、下記のとおりです。
- 現状分析
- 課題の抽出
- 改善・計画の立案
- 改善施策の実行
- 成果の確認・評価
- 改善
それぞれ説明します。
1.現状分析
まずは、現状を分析し、WEBサイトの改善点を見つける必要があります。分析は、前述した「Google Analytics(グーグルアナリティクス)」などの「解析ツール」を使用しておこなうのが一般的です。
「解析ツール」では、主に次のような指標が確認できます。
- サイトがどれくらい見られているか
- どのような経路でWEBサイトに流入しているか
- どこに住んでいるユーザーが多いか
- ユーザーの年齢や性別はどうわかれているか
- ユーザーはサイト内でどのような行動をしているか
これらを見ることでWEBサイトの現状把握が可能です。
2.課題の抽出
サイトの現状分析をおこなったあとは、分析データに基づいた課題を抽出していきます。課題を抽出していく過程では、WEBサイト改善の目的を振り返りながらおこなうことが重要です。
3.改善・計画の立案
抽出した課題をもとに、具体的な改善・計画を立案します。
例えば、ECサイトを運営していて商品購入が目的の場合は次のような立案がおすすめです。
| 課題 | 商品をカートに入れるだけで購入に至らない(カートに入れるユーザーは50人いるのに、そこから購入するユーザーは2人しかいない) |
| 改善策 | 購入ページのリニューアル |
| 計画案 | 新規ユーザー用の入力項目を減らす、購入最終画面に合計金額をわかりやすく表示させる、など |
4.改善施策の実行
改善・計画の案が完成したら、改善施策の実行に移ります。多くの場合、複数の課題が見つかるため、優先順位を決めておくとよいでしょう。売上に直結するものから優先的に取り組むのがおすすめです。
5.成果の確認・評価
改善施策の改善策を実施し、1週間から1ヵ月程度日数が経過したら、成果の確認・評価をおこないます。解析ツールを使い、蓄積されたデータで効果を測定しましょう。
6.改善
WEBサイトの改善は、施策をおこなったら終わりではありません。PDCAサイクルを繰り返して、継続的にサイトを改善し続けることが大切です。また、ユーザーやニーズの変化にも随時対応していく必要があります。
WEBサイト改善の提案準備

WEBサイト改善の提案をする場合、下記の準備をしておくとよいです。
- 目的を整理し明確にする
- サイトの現状と課題の把握
- サイト改善によるメリットなどを明確にする
それぞれ解説します。
1.目的を整理し明確にする
初めに、WEBサイト改善をおこなう目的を整理し、明確にします。何のために改善するのかを提案書作成の前に整理・明確化しておくことで、わかりやすく説得力の高い提案書に仕上げられます。
2.サイトの現状と課題の把握
分析ツールを活用し、WEBサイトの現状と課題をしっかり把握しておくことも重要です。また、社内メンバーやユーザーから意見・要望をもらうことでも、現状・課題の把握が可能です。課題の分析度合いによって改善効果の大きさが変わるため、注力する必要があるでしょう。
3.サイト改善によるメリットなどを明確にする
WEBサイトの改善には、コストがかかるなど一定のリスクがともなうケースもあります。その場合、リスクよりメリットが上回るなら、改善を実施すべきという判断ができます。
例えば、コンバージョン数が月間10件程度しか増えないのに50万円かかるとなると実施の判断には至らないかもしれません。一方、コンバージョン数が月間200件増加する施策のコストが50万円だった場合ではメリットが大きいため、前向きに検討されるでしょう。
WEBサイトの改善によってもたらされるメリットや、リスク・コストを明確にすることで、実施すべきかどうかの判断がしやすくなるといえます。
改善提案書を作成する

次に、改善提案書の作成方法を解説します。手順は下記のとおりです。
- 現状の問題点を具体的に記載する
- 問題点解決への行動案や改善策を提示する
- 必要コストや労力の記載
- 改善目標を数値で記載する
- スケジューリングをする
それぞれ説明します。
1.現状の問題点を具体的に記載する
初めに、現在どのような問題があるのか、その内容を記載します。その際、問題点を指摘するだけでなく、それによってどのような損害をもたらしているのか、またどういった条件で起こっているのかといった点をできるだけ具体的に記載するのがポイントです。問題点が具体的に書かれていることで、改善案に納得してもらいやすくなるでしょう。
2.問題点解決への行動案や改善策を提示する
続いて、問題点を解決するための行動案や改善策を提示します。どう考えても実行不可能な行動案・改善策を提示しても意味がないため、必ず実行が可能な施策を記載するようにしましょう。
3.必要コストや労力の記載
解析に使うツールが有料の場合など、コストがかかる改善策を提示するときは、必要となるものを概算や購入先と合わせて記載しておきます。また、改善に欠かせない人員やおおよその所要時間に関してもあらかじめ記載しておくことが大切です。
4.改善目標を数値で記載する
次に、改善の目標を数値で記載します。ユーザー獲得数やコンバージョン率など、改善目的に合わせた目標数値を設定しておきましょう。
5.スケジューリングをする
最後に、改善実施のスケジュールを立てて記載します。この場合、できるだけ余裕を持たせたスケジューリングがポイントです。リスケジュールの可能性も加味しておくことをおすすめします。
サイト改善を提案する際のポイント

WEBサイト改善を提案する際は、ポイントを押さえておくとスムーズに進みます。
把握しておくべきポイントは、下記の6つです。
- 納得できる根拠を提示する
- 操作画面を共有しながら提案する
- 修正案は抽象的ではなく具体的に
- クライアントに修正の完了連絡を依頼しておく
- 施策提案の意図を理解しておく
- サイト改善以外の改善案も織り交ぜる
それぞれ解説します。
1.納得できる根拠を提示する
改善の根拠を提示する際は、誰もが納得できる客観的な内容にしておく必要があります。例えば、広告管理画面の数値や分析ツールで確認できるデータなど、「数値的な根拠」なら客観性を持った提示が可能です。また、数値的根拠を出すのが難しい場合、「一般論をもとにした根拠」を提示してもよいでしょう。
次のようなケースでは、WEBサイトがターゲティングしたユーザーに適していないと一般的に考えられるため、改善が必要な根拠となります。
- 高齢者をターゲットにした商品のサイトなのに、文字サイズが小さすぎる
- 水漏れ対応などの緊急性の高いサービスのサイトなのに、電話番号の部分がタップできない
- 高級な商品を販売するサイトなのに、詳しい会社情報が掲載されておらず、信頼しにくい
2.操作画面を共有しながら提案する
WEBサイトの挙動やデザインなどの話は、口頭だけでは伝わりづらいものです。納得感を持ってもらうためには、直接パソコンやスマートフォンの画面を見せながら操作して提案するのがおすすめです。アプリなどを利用して録画をおこない、その動画を共有する方法もよいです。
3.修正案は抽象的ではなく具体的に
改善策は、あとで修正するケースもあります。その場合、修正案は抽象的ではなく具体的なものにすることが重要です。テキスト部分の修正なら具体的な文章を、デザインに関する修正部分ならラフデザインを提案しましょう。全体ではなく、部分的な改善提案を作成するときは、「AUN」などWEB上のツールを利用すると便利です。
4.クライアントに修正の完了連絡を依頼しておく
効果検証の際は、修正したタイミングを知っておく必要があります。そのため、改善後に実施する効果検証を見据え、修正の完了連絡をクライアントに依頼しておくとスムーズです。
また、WEBサイトの修正でどれくらい改善したのか、という結果を提示することで、今後のサイト改善提案が進みやすくなります。
5.施策提案の意図を理解しておく
WEBサイトを改善する場合、コンバージョン率を改善させるための施策なのか、SEOのための施策なのかなど、方向性が異なるケースがあります。優先度は状況によって異なりますが、それぞれの可能性を把握しておくとよいでしょう。一つひとつの施策の意図を理解しておくことで、複合的な提案がしやすくなります。
6.サイト改善以外の改善案も織り交ぜる
WEBサイトの改善だけでなく、他の改善案も織り交ぜることが大切です。基本的にWEBサイトの改善はクライアント側でおこなうため、「こちらでやることが多くて負担がかかる」と思われがちです。
そのため、広告の改善案を提示したうえで、相乗効果でさらに成果を上げる施策という形でWEBサイト改善を提案するのがおすすめです。
まとめ

WEBサイト改善は、企業の成長や拡大を目指し、「お問い合わせ(CV)を増やす」「認知を拡大させる」「利益を上げる」などを目的としておこなわれます。改善の効果を最大化するには、目標・目的やニーズに基づいた施策の検討が必要となり、企業によって改善施策は外部と内部に分けられます。
WEBサイトを改善する際は、現状分析、課題の抽出、改善・計画の立案、改善施策の実行、成果の確認・評価の流れでおこなうのに加え、随時改善していくことも重要です。
また、WEBbサイト改善の提案は、誰もが納得できる根拠を提示したり、操作画面を共有したりするなどのポイントを押さえておこなうとよいでしょう。ぜひ、今回の記事を参考にしながら、WEBサイト改善を積極的に提案してみてください。
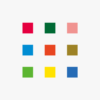
タガタメの編集部です。読んで頂いた人がすぐ行動できるメディアを目指し、サービス提供を通じて汎用的で皆さんがすぐ使えるノウハウや情報を発信していきます。
おすすめ記事
タガタメでは一業種一社限定の
WEBコンサルティングを提供。
・どんな広告が良いのか悪いのか分からない
・サイト改善してコンバージョン率を上げたい
・担当者への要望がなかなか反映されない
お気軽にお問い合わせください。