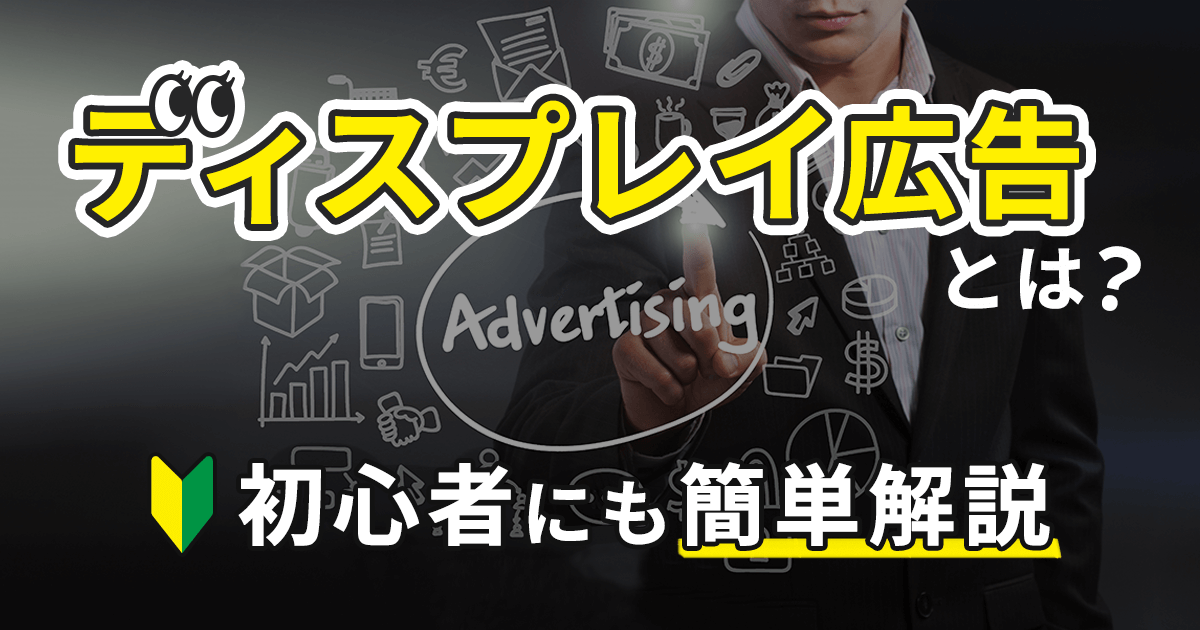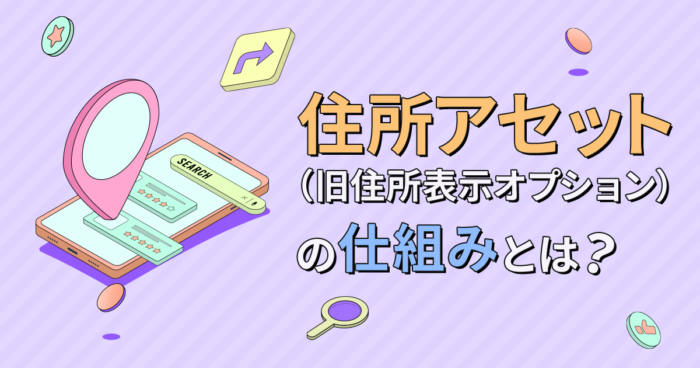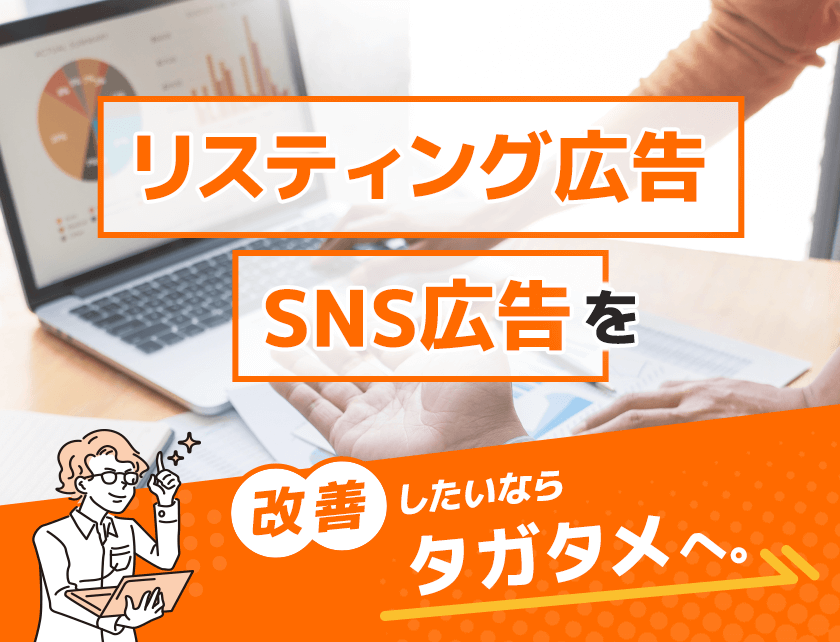広告の運用において、リスティング広告と並んでポピュラーなものが「ディスプレイ広告」です。ディスプレイ広告は「バナー広告」とも呼ばれており、画像や動画などで掲出されます。
ディスプレイ広告とは?
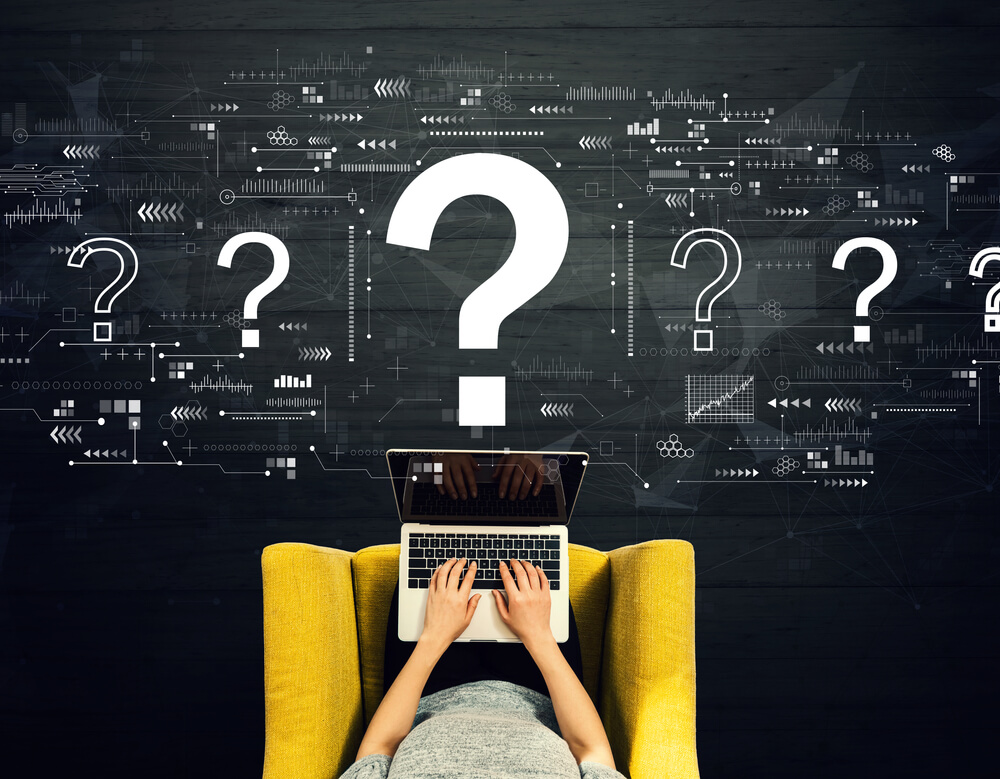
検索サイトYahoo!JAPANトップページの、四角い広告枠を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。ディスプレイ広告はWEBサイトやアプリなどの広告枠に表示されるもの。リスティング広告は検索ワードに連動しており、顕在化しているターゲットに有効です。一方、ディスプレイ広告は潜在層にも効果が見込める広告手法。
それでは早速、ディスプレイ広告の種類やメリットなどを見ていきましょう。
ディスプレイ広告の種類
あらゆるWEBサイトやアプリにディスプレイ広告枠が存在します。主にGoogleとYahoo!JAPANの2大アドネットワークが活用されており、多くの広告主が出向しています。
Googleディスプレイネットワーク(GDN)
GmailほかGoogleが提供しているサービスに広告が配信されます。また、Googleが提携しているサイトにも配信。対象先は200万以上で、WEBサイトのみならずアプリや動画プラットフォームなど、さまざまなコンテンツに配信が可能です。
Yahoo!ディスプレイ広告【運用型】(YDA)
Yahoo!ディスプレイ広告は、多くの人がデスクトップに設定しているYahoo!JAPANやYahoo!ニュース、Yahoo!知恵袋などを中心に配信される特徴があります。Googleと同様、提携するその他サイトにも配信されます。
YouTube広告
Google、Yahoo!JAPANがネットワークを活用して幅広いサイトに配信するのに対し、一つのプラットフォームに特化して掲出するディスプレイ広告もあります。代表的なのがYouTube広告。ユーザーが視聴する動画の前に広告の配信が可能で、トップページや検索結果に掲出ができます。
ディスプレイ広告のメリット
次にディスプレイ広告のメリットを見てみましょう。キーワード検索によるテキストの訴求ではないディスプレイ広告は、大きく分けて6つのメリットがあります。
1.視覚表現によるブランディングが可能
リスティング広告との大きな違いはビジュアルです。テキストで訴求するリスティング広告に対して、ディスプレイ広告は画像や動画といった視覚表現が可能。直感的な訴求効果を見込むことができるので、企業やサービスのブランディングに最適です。
2.さまざまな目標に合わせたキャンペーン展開
圧倒的に表現の自由度が高いリスティング広告。つまり、目的に合わせたキャンペーン展開が可能です。中長期的なブランディング戦略はもとより、インパクトのあるビジュアルとテキストを合わせてタイムリーに集客ができます。
3.最適なユーザー層を見つけてくれる
単純に不特定多数のサイトに配信するだけではありません。ユーザーの年齢や性別はもちろん、趣味嗜好の指定などもセグメントができます。マス広告として幅広いユーザーへのアプローチや、最適なユーザーに効率的に配信することも可能です。
4.リターゲティングできる
きめ細かなターゲティングのなかでも有効なのがリターゲティングです。一度バナーをクリックしたユーザーや指定のサイトにアクセスしたことがあるユーザーに、再度配信する手法。ユーザーと広告の接触回数を増やし、効率良くコンバージョンを得るプロモーションが期待できます。
5.自動可による効率化、掲載結果の改善
ディスプレイ広告は配信先や配信コストなどが自動化できます。過去の実績から効果が見込める広告枠に、効率良く配信が可能。例えば「サイトAはアクセス、コンバージョンともに良好なので継続」、「サイトBからのアクセス数は多いが、コンバージョンは少ないので、ビジュアルを変更」、「サイトCはアクセス見込めないため、サイトDへシフト」など、掲載結果の改善にも役立ちます。
6.クリック単価が安い
ターゲティング方法によって変動しますが、クリック単価が安価なのもディスプレイ広告のメリットでしょう。リスティング広告は具体的なキーワードに入札します。相場は1クリック10円から数100円ですが、人気のキーワードはさらに高くなる傾向にあります。一方、ディスプレイ広告の1クリックの相場は数10円程度。限られた予算で、多彩なプロモーションを試すことができるでしょう。
ディスプレイ広告のデメリット
デジスプレイ広告には、いくつかデメリットもあります。まず挙げられるのがCTR(クリック率)の低さです。リスティング広告は、能動的にキーワードで検索する購買意欲の高いユーザーに配信ができます。一方、ディスプレイ広告は潜在層に対する告知。いわゆる受動的な広告となるため、CTRは低い傾向にあります。
また、幅広いクリエイティブと配信パターンがあるため、最適解の見極めが難しいのもデメリット。高い訴求効果が見込めるクオリティの高いバナーデザインを制作しても、ターゲティングとマッチしていなければ効果は薄くなります。反対に、精度の高いターゲティングが実現できたとしても、クリエイティブが適切でないこともあるでしょう。そもそも訴求する商材がディスプレイ広告のプロモーションと合っていないケースも考えられます。
これらのメリット、デメリットを理解したうえでディスプレイ広告の検討が大切です。
Google ディスプレイネットワークの仕組み
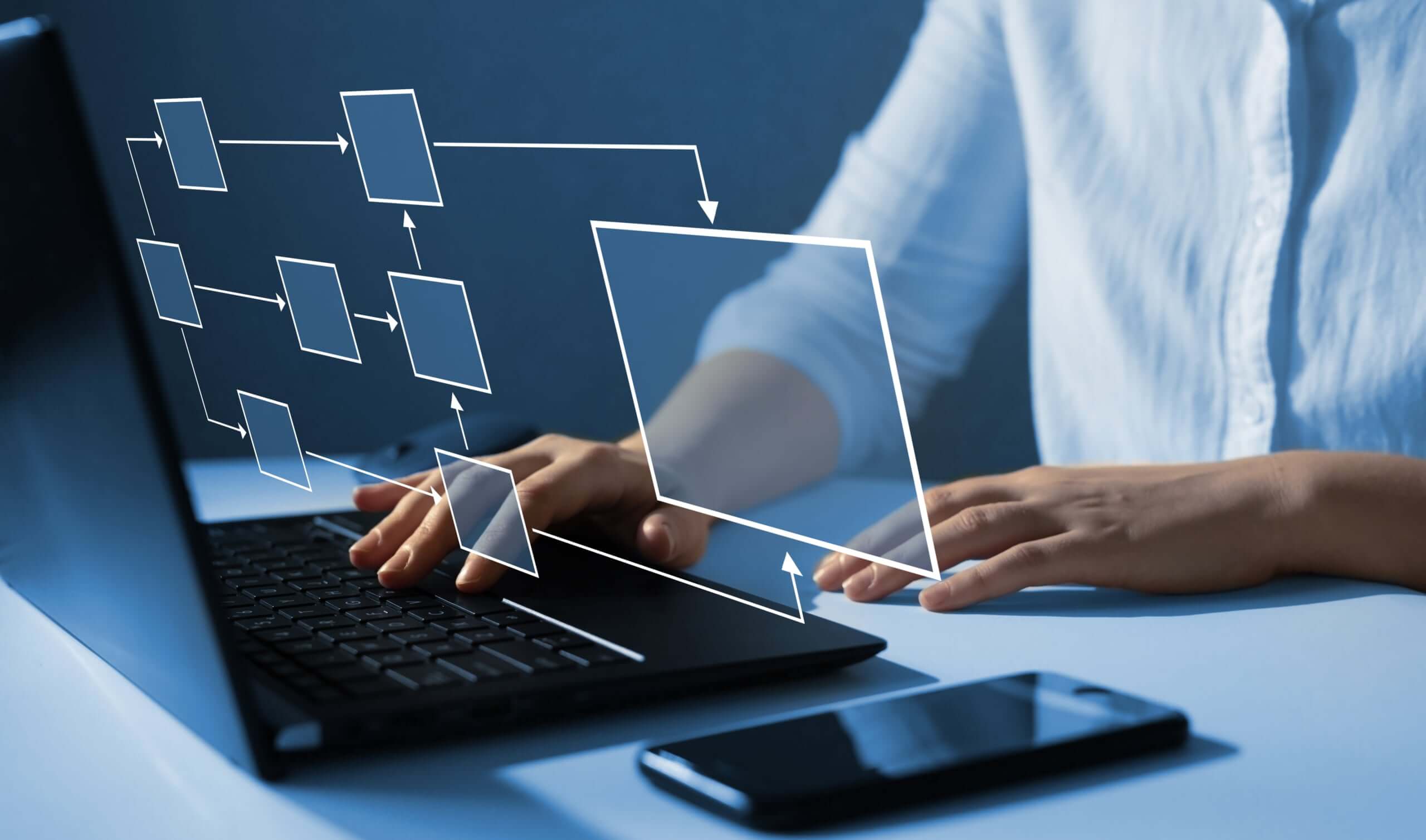
さて、続いてディスプレイ広告のなかでも多くの広告主が活用しているGoogle ディスプレイネットワークについて解説していきます。
広告表示のタイミング
Google ディスプレイネットワークは基本的に、ユーザーがサイトを閲覧したときにランダムで表示されます。ディスプレイ広告枠が複数あるサイトは、掲出される場所も異なります。各ディスプレイ広告枠はサイズが異なるため「レクタングルバナーはビジュアルに特化」、「320×100のミニバナーはテキストで訴求」などと使い分けたほうがよいでしょう。
ターゲット設定を使ったアプローチ例
ターゲット設定でまず考えなくてはならないのは、どのようなサイトに配信するかです。広告を配信するサイトはURL単位で設定が可能。最も高い効果を見込めるのは実績です。「過去、サイトAからの流入数とコンバージョン率が好調だった」という実績があればサイトAを配信先に指定できます。
また、広告内容と親和性の高いサイトに絞って配信ができるのも特徴。例えば、高級腕時計が商材だったとします。高級腕時計を購入しそうなユーザーが多く閲覧しているサイトに配信するアプローチ。この場合、腕時計の比較サイトはもちろんですが、高級車の紹介サイトや旅行系サイトなども狙い目でしょう。
もちろん、流入やコンバージョンが見込めないサイトの除外も可能です。Google ディスプレイネットワークを活用した配信先サイトは無数にあるので、効果が見込めないサイトは除外していくのがベターです。
セグメントを使用したアプローチ
上記は「どこに出すのか」を考えたアプローチですが、次に「誰に出すのか」を考えてみましょう。Google ディスプレイネットワークではユーザーのセグメントが可能です。セグメ「年齢」、「性別」、「世帯収入」、「子どもの有無」、「アフィニティカテゴリ」、「類似ユーザー」、「リターゲティング」などがあります。
「年齢」は18〜24歳、25〜34歳、35〜44歳、45〜54歳、55〜64歳、65歳〜と詳細に設定できます。「アフィニティカテゴリ」ではユーザーの興味関心を138項目から選択可能。「ニュース、政治」、「フード、ダイニング」、「スポーツフィットネス」、「美容、健康」などがあります。
これらを組み合わせて、商品やサービスに興味を持ちそうなユーザーへアプローチができます。例えばプロモーションする商材を“主婦向けのフィットネスクラブの会員募集”と仮定しましょう。「30〜70歳」、「女性」、「美容、健康」、「スポーツフィットネス」、「類似ユーザー」、「リターゲティング」を設定します。これで「30〜70歳の女性で美容、健康、スポーツフィットネスに興味関心を持っているユーザーに広告を配信し、かつバナーをクリック(閲覧)したユーザーに再度配信ができ、バナーをクリックしたユーザーに類似するユーザーにも配信できる」という設定になります。
自動化機能によるアプローチ
きめ細かにターゲティング設定ができる反面、セグメントし過ぎると配信できるユーザー数が少なくなってしまいます。また、的確なターゲティング設定をしていないといつまで経っても流入数やコンバージョン率は増えません。そこで役立つのが「自動化機能」です。
これは設定したリストやキーワードに基づいて拡張されていく機能。リターゲティングリストに新車販売サイトを入れていたとします。すると、新車販売だけでなく中古車販売サイトにアクセスしたユーザーにも配信される仕組みです。また、キーワードを指定して拡張すると、新車や中古車だけでなくカーシェアやサブスクリプションサイトなども配信対象になる可能性があります。
レスポンシブディスプレイ広告
配信先だけでなくクリエイティブも自動化ができます。これをレスポンシブディスプレイ広告と呼びます。本来、バナー広告は広告枠のサイズに合わせて入稿しなければなりません。サイズが異なる広告枠には配信できなくなります。しかし、レスポンシブディスプレイ広告であれば、入稿した画像やテキストのサイズやフォーマットが自動的に調整されます。
その他のディスプレイ広告の種類
ディスプレイ広告は一般的に画像をメインとした「バナー広告」や「テキスト広告」がスタンダード。近年ではより訴求効果の高い「動画広告」も増えてきています。また、コンテンツに挟まれる形で配信される「インフィード広告」も注目を集めているディスプレイ広告。SNSタイムラインやメディア記事の間に、違和感なく同じようなフォーマットで配信されます。サイトを閲覧しているユーザーにとって、ディスプレイ広告は避けられがち。インフィード広告であれば、コンテンツの一部としてクリックする可能性が高まります。
キャンペーン作成は計画的に

特にGoogle ディスプレイネットワークで自動化機能を扱う場合、キャンペーン作成は計画的におこなうのが好ましいでしょう。自動化機能は新規顧客開拓やコンバージョンの可能性が高いユーザーに積極的にアプローチできるメリットがある一方、ブランドイメージにそぐわないサイトへ配信してしまうこともあります。新しいサイトに展開していくことでコストを消費してしまい、コンバージョンが獲得できるユーザーへの機会損失を招いてしまうことも。
プロモーションする商材の特性をしっかり理解し、運用者のペースで配信先サイトやユーザーのセグメントを実施していくことが大切です。
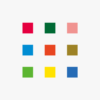
タガタメの編集部です。読んで頂いた人がすぐ行動できるメディアを目指し、サービス提供を通じて汎用的で皆さんがすぐ使えるノウハウや情報を発信していきます。
おすすめ記事
タガタメでは一業種一社限定の
WEBコンサルティングを提供。
・どんな広告が良いのか悪いのか分からない
・サイト改善してコンバージョン率を上げたい
・担当者への要望がなかなか反映されない
お気軽にお問い合わせください。